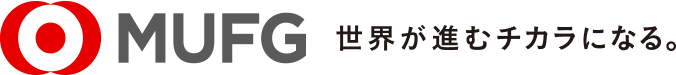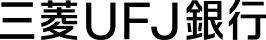2025.03.31
ITには無限の可能性がある。
未来を見据えた基盤を創り出そう。
未来の自分から逆算し、「今、なすべきこと」を
大学・大学院で電子工学を専攻し、半導体に関する研究を行っていた私は、就職を機にITの世界へ飛び込むことを決意しました。その理由は、この世界ならではの劇的な進化スピードにありました。どちらも社会にとって欠かせない分野ですが、ITの分野なら、自ら新たな価値を生み出し、より早く世の中に届けることができると考えたからです。
新卒で入社したのは、国内大手の通信会社でした。研究所に所属し、ネットワーク・サーバ領域の研究開発を任されていました。サーバ仮想化技術の研究開発や、社内向けプライベートクラウドの開発・運用、検証自動化システムの開発・導入、5Gモバイル網のコントローラ制御装置の研究開発など、世の中に必要不可欠な通信の世界で「イノベーションの種」を創り出す仕事に確かなやりがいを感じ、自らの専門性を磨くことができたと自負しています。
転職を決意したのは「自らが理想とするキャリア」を実現する最適な環境を求めてのことでした。30代になり、プレーヤーの立場からチームや組織をまとめる立場になっていく中で、40代・50代になったときに「どうありたいのか」を突き詰めて考えるようになったのです。メンバーの意欲を尊重し、チームのパフォーマンスを最大化していくマネージャーは非常に価値のある存在だと思います。しかし、私は自らもプロフェッショナルとして、技術面でもチームをリードしていける存在になりたかったのです。そして、そのために今、どのような仕事をすべきかを考えました。
ゴールから逆算して導いた結論は、自らの専門性を駆使して、エンドユーザーに対して明確なアウトプットを出す30代を過ごすことでした。そこで、私が最も期待するポジション・役割を提示してくれたのが三菱UFJ銀行でした。日本最大の金融機関で多くの人にその価値を提供できること。一つのミッションや所属部署に縛られることなく、自由にチームをまたぎながら、最大限のパフォーマンスを発揮できること。フラットで刺激に満ちたカルチャーのもと、ここでしか経験できない使命感のある仕事ができることは何よりの魅力です。

日本最大の金融機関を支える「重責」を胸に
私の所属するネットワーク・クラウドサービス部は、三菱UFJ銀行のシステムを支える基盤を担うチームです。サービス開発を担う部署からの要望を受けて、MUFG全体のネットワーク、AWSなどのクラウドサービス、コンテナプラットフォームを開発・運用することが主なミッションです。私が担当するのは、AWS上に構築されたコンテナプラットフォームの開発および運用です。具体的には、ゲストの開発計画や要件に合わせた設計・機能検証や構成変更、機能の問い合わせへの回答、構築運用作業の自動化の仕組みを開発する業務が中心となります。さらに、ITコントロールサービス部での業務も兼務しており、コンテナプラットフォームを含む各種システム基盤全体をどう管理・提供していくか、将来像の実現に向けた開発にも参画しています。
日本最大の金融機関を支えるシステムは実に巨大です。膨大なトランザクションの数を見るだけでも圧倒されるほどで、それだけ多くの人々の暮らしやビジネスを支えていることを実感します。私たちは、それらのシステムが止まることのないよう最善を尽くしています。
特に印象に残っているのは、入社して数ヶ月たったころに経験したコンテナプラットフォームの障害対応です。幸いにも影響範囲は小さく、すぐに復旧することができましたが、その対応への姿勢には、これまでに経験したことがないほどの緊張感を抱きました。マネジメント層も含めたすべての関係者が一堂に会し、影響確認や原因解析を進めていく姿に、システムの安定稼働やサービス影響に対する責任の大きさを実感しました。

ミッションクリティカル。だから、本質的な価値創造に挑む
「止まることが許されない」「失敗が許されない」。そう言われると、新しい技術を使えない、チャレンジしにくい環境と思われる人も多いかもしれません。しかし、三菱UFJ銀行のシステムを支える仕事に伴う「責任」は、一人ひとりのチャレンジを阻害する要因ではありません。決められたルーティンワークをこなすだけでなく、改善や挑戦を後押ししてくれる風土は、この会社が持つ大きな魅力だと感じています。
誤解を恐れずに言えば、機械は必ず壊れるものであり、ソフトウェアにもバグがつきものです。それらをいかにして未然に防ぐのか。そして、障害が発生したときにはなぜそれが起きたのか、どうすればそれを防ぐことができるのかを突き詰めていくことが大切です。だからこそ、私たちは担うべき責任にポジティブに向き合っています。このチームでは「自らが担当するシステムをどうしていきたいのか」「抱えている課題をどうやって解決するのか」という不定形な取り組みに対して創意工夫しながら解決していくことが求められます。それは、エンジニアとして無二の楽しみであり、喜びでもあります。実際に私自身、入行して1年未満のうちに、コンテナラインの改善策やツール群の見直しなど、さまざまな提案・改善機会に恵まれています。
私たちが担当するネットワークは、社会を支え、当行の飛躍を担う未来への基盤です。現在、三菱UFJ銀行では、現行のシステムをモダナイゼーションするアーキテクチャ計画を打ち出し、ここ十年で多額の投資を行っています。その計画において、今後はこれまでにない新しい技術を駆使する機会も増えていくことでしょう。しかし、技術はあくまで手段であり、すべてを新しいものにすればいいという単純なものではありません。大切なのは、あくまで目的です。より安定的で、セキュアで、生産性の高いシステムを実現するために、私たちは「より良い価値」の実現をめざしています。それぞれのメンバーが持つ専門性を最大限に発揮し、今の仕事にとらわれるだけでなく、未来のあるべき姿を実現する価値を創り出す。そうした仕事ができる環境は、これ以上ないやりがいを与えてくれるものだと実感しています。

エンジニアにとって、最高の環境を創りたい
私はエンジニアであるとともに、二人の子どもの父親でもあります。保育園の送り迎えはもちろん、急に体調を崩すことも多いのですが、現在の職場ではしっかりと周囲のサポートを受けることができ、在宅勤務なども積極的に活用しています。ただし、こうした支えを受けられるのも、私たちの職場が高い生産性で働きやすい環境が整っているからです。どれほど優しく、思いやりに満ちた人が集まっていても、仕事が忙しく、サポートする余裕がなければ、思いやりや支え合いは実現できません。
今後の目標は、この素晴らしい環境をさらに進化させ、エンジニアがモチベーション高く貢献できる最高の環境をつくることです。ITには無限の可能性があると確信しています。その力を最大限に活用して業務をさらに効率的にし、すべてのエンジニアが心地良く開発・運用に打ち込めるようなエコシステムをここで実現したいと考えています。
三菱UFJ銀行は、IT人材のキャリア採用に力を入れています。さまざまな価値観や経験を持った人の存在は、私たちに新たな気付きをもたらし、組織のイノベーションを促進してくれるものだと思っていますし、私自身もそうした好影響を与えられるように意識してきました。そして、ここで生まれた小さな革新は、システム部門にとどまらず、行内全体にも良い影響をもたらす価値があると考えています。それぞれが持つ専門性を最大限に発揮し、誰もが幸せに仕事ができる「最高の環境」をともに実現していく。そんな日を心から楽しみにしています。
Profile
※所属およびインタビュー内容は
取材当時のものです。

伊藤 義人
三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社
グループ共通基盤本部 ネットワーク・クラウドサービス部 プロフェッショナル
2024年入行
大学院修了後、大手通信会社の研究所でネットワーク・サーバ領域の研究開発に従事。2024年に三菱UFJ銀行に入行し、三菱UFJインフォメーションテクノロジーに出向。クラウドサービス上でのコンテナプラットフォームの開発・運用を担う。
この行員に関連する職種に申し込む