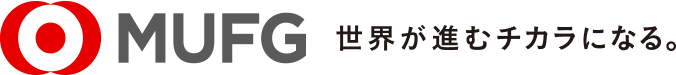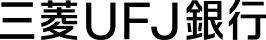2025.03.31
これからは転職をしなくても
新しいキャリアにチャレンジできる。
長期的な視点でユーザーに向き合いたい
就職活動や転職を検討する際、私は常に「自らの市場価値を高め、どこに勤めても通用する人材になる」ことを意識していました。キーワードとして「金融」「IT」「コンサルティング」を持っていました。
新卒では、法人・個人双方にとって不可欠な「金融」の知識を身につけるために政府系金融機関に就職し、法人営業担当者として経験を積みました。その後、「IT」と「コンサルティング」の要素を加えるために、機関投資家向けのアプリケーションを開発する会社に転職し、専門性を高めました。さらに、外資系コンサルティングファームや国内大手SIerでSalesforceを活用したシステム開発・ITコンサルティングに従事しました。
コンサルティングファームやSIer時代は、EC運営、小売などのお客さまに対するコンタクトセンターCRM(顧客情報管理)領域のプロジェクトが中心でした。金融から離れることに悩みましたが、20代だったこともあり、Salesforceに軸足を置くことを決断しました。システム構想策定などの上流工程から開発までのフェーズを担当していましたが、一つのプロジェクトが終わるたびに別のお客さまのプロジェクトへ参画する関わり方に疑問を感じるようになりました。プロジェクトが終わった後も、そのシステムが正しく利用されているか、満足度高く使われているかを長期にわたって確認したいと考えるようになりました。
そこで、事業会社でSalesforceの経験を活かすことを軸に転職活動を開始しました。その中で三菱UFJ銀行に多くのシステムが存在することを知り、その多様性と規模に挑戦の可能性を感じました。説明会では「アジャイルへの挑戦」「レガシーシステムからの脱却」といったキーワードが強調され、会社全体で新しいことに果敢に挑戦している姿勢が伝わってきました。また、内定後に配属予定部署の責任者からプロジェクトの内容や私の役割、業務内容を詳しく教えてもらい、入行後のギャップが一切なく、安心して業務を開始することができました。

パッケージ導入に対して想像以上に柔軟
現在、私は法人および個人のお客さまを担当するRM(Relationship Manager)が利用するCRMシステムの新規構築を担うチームに所属し、主にフロントエンドの開発を担当しています。チームは内製開発ラインとビジネスパートナー(BP)による開発ラインに分かれており、私はサブリーダーとして後者のラインを担当しています。そこではユーザー部門の要件を整理し、その実現に向けてBPと最適な仕様を検討し、バックエンド開発チームや行内の他システムとの調整を行っています。ており、私はサブリーダーとして後者のラインを担当しています。そこではユーザー部門の要件を整理し、その実現に向けてBPと最適な仕様を検討し、バックエンド開発チームや行内の他システムとの調整を行っています。
例えば、Salesforce内のBIツールなどのUIを向上させるTableauは別の担当者が主管しているため、その担当者との調整が必要になります。また、入力したデータはすべて当行のシステムに集約するため、バックエンド開発チームを介してそのシステムの担当者とのやりとりも発生します。
ユーザー部門の要件はさまざまです。例えば各RM個人の実績管理に関わる部分はSalesforceでは要件を満たせないためカスタマイズを行います。正直に申し上げると、私は銀行がパッケージ製品を使うイメージを持っていませんでしたが、実際はパッケージ導入に対して非常に柔軟でした。「すべて一からつくっていく」という文化を想像していたので、その先入観と比べると、PoCの段階から「これはパッケージで対応できる範囲で問題ありません」と判断してもらえる場面が多々あることは驚きでした。もちろん、巨大かつ重厚なシステムですから、銀行としてこだわりの強い部分はカスタマイズしますし、その量は膨大です。しかしながら、そのようなメリハリがあるというだけでも私にとっては意外でした。

経験したことがない長期プロジェクト
もう一つ実感したのは、プロジェクトにかける期間の長さです。現在進めているCRMシステムの新規構築は、近々初回のリリースを迎えます。まず、Excelなどで行っていたメイン業務を新しいシステムに移行し、その後セカンド、サードとステップごとに大規模開発を予定しています。そもそもファーストステップも私が入行する前から進んでおり、3年ほどの期間を要しました。今後も数年をかけての開発を見込んでいます。前職までのプロジェクトは最長でも1年でしたので、これほどじっくり進める開発を経験したことはありません。
大規模システムに必要なプロジェクトの多さ、金融機関だからこそ求められるセキュリティの堅牢性など、検討が必要な要素はたくさんあります。例えば、自分が担当するラインの機能を一部変更する場合でも、その影響は広範囲に及びますので、関係する部署との緊密なコミュニケーションが欠かせません。その調整には前職までとは違う難しさがありますが、自分自身のコミュニケーション能力や調整力を向上させる良い機会だと捉えています。

働きやすく、一丸となって解決に向かう風土
業務内容については入行前後でギャップはありませんでしたが、働き方については良い意味でギャップがありました。在宅勤務が可能であることは入行前に聞いていたものの、形だけではなく実際にしっかり利用されています。時差出勤や育児休業取得についても同様で、想像以上に働きやすい環境だと感じています。
私の場合、週に2日ほど在宅勤務を活用しつつ、チームで一斉に出社する日を決め、各種ミーティングや調整を行っています。また「人が少ない朝に集中して業務を進めたい」「朝や夕方にプライベートの用事がある」などの場合に時差出勤を活用しています。時差出勤の使い方は人それぞれですが、お子さんの保育園への送迎に活用している方が多いようです。育児休業もメンバーと話し合って時期を決め、入行1年後という早いタイミングにもかかわらず気兼ねなく取得することができました。
風土面でもう一つ感じているのは、建設的な議論を通じて問題を解決していく文化があるということです。例えばシステムを検証する中でなんらかのミスがあった場合、誰かを責めるのではなく、根本原因や解決策をチーム一丸となって議論していきます。
障害発生時の影響は甚大ですし、システム保安室に入る際には何重もの手続きがあるなど、金融機関ならではの緊張感は常にあります。一人ひとりの責任の大きさは言うまでもありませんが、その責任の大きさは自己成長につながりますし、責任を個人に負わせるのではなく関係者全員で担っています。全員で話し合い解決していこうという風土は一人ひとりに安心感を与え、挑戦を促してくれていると感じています。
開発以外にもキャリアを広げられる
私はこれまでソリューションを軸に専門性を磨いてきました。現在はそのソリューションを使ったシステムの開発に従事していますが、当行としてそのソリューションを使い続ける保証はありません。他のシステム開発などにキャリアの軸足を移す可能性も十分にありますし、その可能性は転職時に織り込み済みです。これまで培った専門性を活かしながらも、今後は他のシステムや銀行業務の知見を身につけていく必要があるでしょう。
当行にはさまざまな特徴を持った膨大な数のシステムが存在するため、自分の担当するシステムだけでなく、関係するシステムも考慮して開発できる環境が整っています。さまざまな知見を身につけることで、ユーザー部門に対して全体最適な提案を行うことが当面の目標です。
一方で、開発以外のキャリアも視野に入れています。例えば、当行であれば将来的にユーザー部門のシステム担当者として活躍することも可能です。まずは開発を継続していくキャリアを描いていますが、いつの日か「新しいことにチャレンジしたい」と思うかもしれません。そのとき、転職をしなくても新しい環境でチャレンジできる当行は、私にとって理想的な職場だと感じています。
Profile
※所属およびインタビュー内容は
取材当時のものです。

山田 真平
三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社
情報本部 データ戦略第四部 プロフェッショナル
2023年入行
2013年に新卒で政府系金融機関に入行。翌年、機関投資家向けのアプリケーション開発を行う会社に転職。その後、外資系コンサルティングファームや国内大手SIerでCRM領域のシステム開発・ITコンサルティングを経験。2023年に三菱UFJ銀行に入行し、三菱UFJインフォメーションテクノロジーに出向。現部署でCRMシステムの新規構築に携わる。
この行員に関連する職種に申し込む